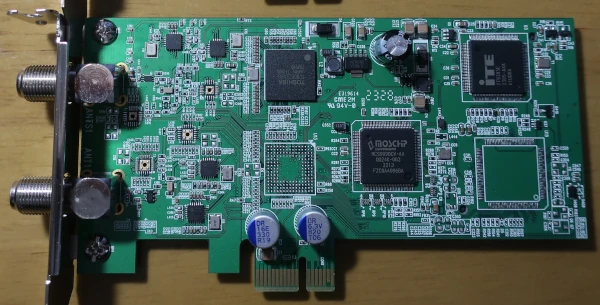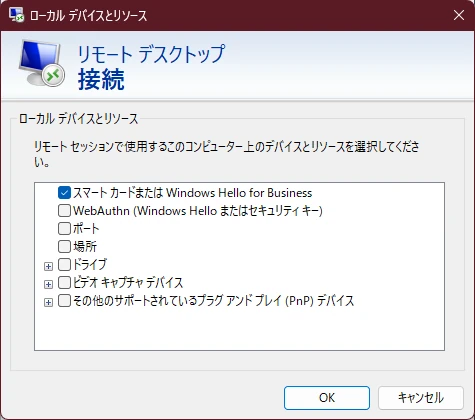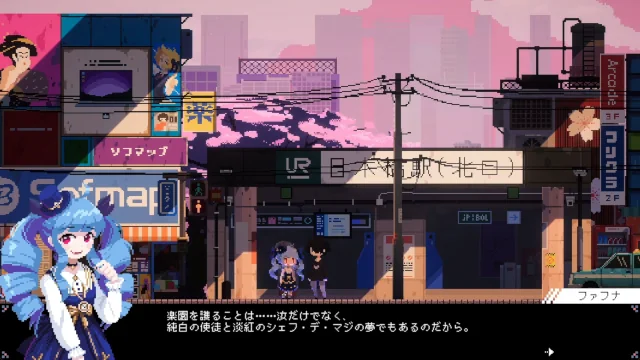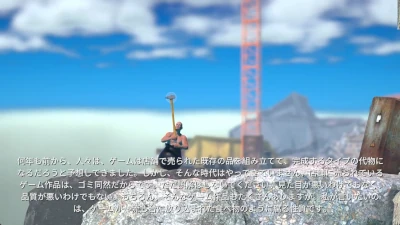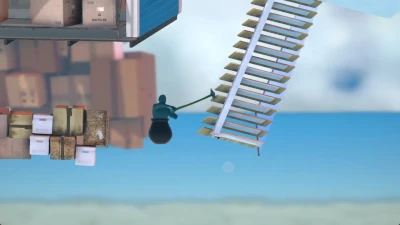最近、家に帰ってきてから寝るまで何をやっていたか思い出せず、生活が充実しているのかいないのかよく分からない。細々とした色々なことに取りかかっていたから、一言で言い表せる成果がまだ出ていないことが要因でしょう。しかし、まだプライベートでやりたいことは山積みなので、優先順位を付けて何か目標を立てておかないと、結果的にだらだら時間を過ごしそうです。
私はバス通勤で、今の路線を5年以上は使っていて何も問題が起きていなかったんだけど、半年ほど前からある女性客が定期的に乗るようになった。彼女のマナーがちょっと問題あって。。。
彼女は片足を骨折しているのか松葉杖をついていて、段差を乗り越えるのが難しいらしい。この路線は全車バリアフリー、前乗り、前払いのバスだが、それでも高さが厳しいらしく、バスを歩道いっぱいまで寄せて、床高さを下げる(「ニーリング機能」というらしい)ことを要求する。ここは運転手や状況によって対応が違って、彼女の言うとおりにする運転手と、車椅子の乗客への対応と同様に後ろの乗り場からスロープを出す運転手がいる。このこと自体は何も問題ない。
次が問題だ。彼女は、財布を出すのに時間が掛かるから運賃の支払いは降車時にしたいと言う。この時の彼女はだいたい、でかマイバッグとスーパーのレジ袋いっぱいの荷物を3~4袋抱えている。ここも運転手によって対応が違って、すんなり要求を受け入れる運転手もいれば、先払いを促す運転手もいる。もしここで先払いを促されると、彼女はごねて自分の意見を押し通そうとし、ここで口げんかになることも時々ある。態度はそこまでキツくないが、「探すので先に出発しててください」と言った後に彼女が財布を探して準備したのを私は見たことがない。私の方が降りるバス停が早いので、彼女が降りるときの支払を注意して見たことがないけども。人種差別に繋がることは軽々しく言うべきでないが、彼女はカタコトが入った日本語を話すので、「俗に入っては俗に随え」の精神があまり根付いていない外国人かもしれない。
口げんかの後では、バス運転手も平温な感情を乱され、少なからず運転に支障が出るだろう。私は帰宅の途でしかこの場面に出会わないので、家に着く時間がちょっと遅れるだけでそこまで迷惑を被っていないが、同じ車内で口論が繰り広げられるのは勘弁して欲しい。
これが一度ならともかく、今後も何度も起きる可能性が高い。小さな火種だって何度も起きれば、いずれ重大な事故に繋がるかもしれない。バス運営会社は組織として対応方針を決めるべきだろう。
![Image: 250125 STG『グラディウス』(1985年)PS4版 [2]最終面が鬼むずかしい](/blog/img/2025/gradiusu-1_250125_4.webp)
![Image: 250119 Seia Limited Pickup (for real!) [r/BlueArchive]](/blog/img/2025/bluaca_250119.webp)
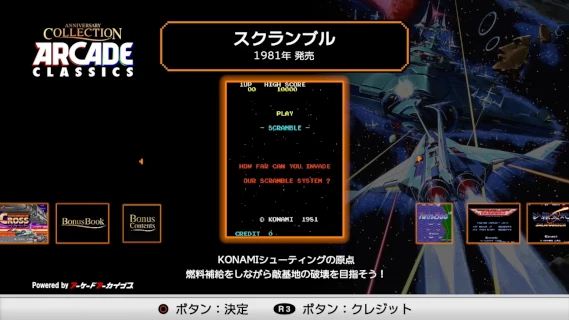
![Image: 250112 AVG『電気街の喫茶店 ふわふわ』[2]エンディングまでと感想](/blog/img/2025/maid-cafe-on_250112_1.webp)